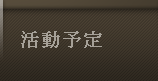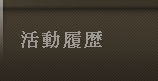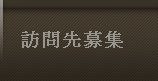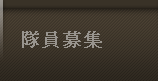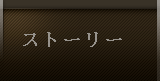ストーリー
第2話:ブルー
第1話← →第3話 →第4話 →第5話 →第6話 →第7話 →第8話 →第9話 →第10話 →第11話 →第12話 →第13話 →第14話 →第15話 →第16話 →第17話 →第18話
「――私の声が聞こえますか?」
声を掛けられたような気がした。聞こえているものは聞こえているので、それには「はい」と答えるしかないのだろうけれど、彼は返答を躊躇した。人を呼び止めるための言葉としては、いささか不自然な感じがする。知り合いを見つけて声を掛けるにしても、知らない人に道を尋ねるにしても、最初に声が聞こえるかどうかを確かめる必要はないはずだ。
だから、これはもしかしたら何かの聞き間違えかもしれない。ここのところ、彼はゼミの予習に追われて寝不足が続いている。しかも今日は、昨日の午後の激しい豪雨に堪えたご褒美のように、五月の爽やかな青空が街を覆っていた。このままずっと眠っていたいと後ろ髪を引く自分の脳細胞に鞭打って、なんとか家を出てきたところだった。
「――私の声が聞こえますか?」
彼は小さく溜め息をついた。間違いなく、声が聞こえるかと問われている。ここはとりあえず、なんらかの応答をせざるを得ないだろう。彼は歩みを止めて、その声の主を探すことにした。ちなみに、声の主がどうやら若い女性であるらしいことは、彼の判断に影響を与えることはなかった(と彼は自分に言い聞かせた)。
おそらく、音源は左斜め後ろの方向。それほど距離は離れていない。できるだけ自然な感じで、口元に嫌らしくならない程度の微笑を作って、彼は振り向いた。
街路樹の新緑に比べて幾分か控えめな薄いペールグリーンのワンピース。肩にかかる真っ直ぐな黒髪。くりっとした両目が印象的で、その瞳はどこまでも深く淡く澄んでいる。清楚という一言には決して押し込むことのできない魅力を纏った少女が、そこには立っていたらいいなと彼は思った。
しかし、残念ながらそんな少女は影も形もなく、ただプラタナスの葉が気持ちよさそうに風に揺れているだけだった。
「下、下、もっと下」
言われるままに視線を下に移すと、そこには白くて丸い物体が落ちていた。それは密度の濃い大きな綿菓子を連想させた。彼は数秒の時間を要して、それが「猫」と呼ばれる生物であることを認識した。
開いた口が塞がらない、という体験を文字通りにしたのは初めてだ。彼が知る限り、この世界では猫はしゃべらない。確かに、例えば彼の思いつく範囲でも、『魔女の宅急便』や『美少女戦士セーラームーン』には、口が達者な猫が出てきたような気がする。設定としてはよくあるパターンに違いない。でも、それらは(きっと)架空の物語であって、現実にはあり得ない話のはずだ。
目の前の猫は、彼と目が合うとにっこりと微笑んだ――ように彼には見えた。 目つきはやや鋭いが嫌な印象は感じない。少し垂れた長めの髭と、ピンと張った小さな耳には、どことなく愛嬌がある。
「よかった。ようやく話の通じる人に出会えた。苦節三日と14時間。苦労した甲斐があったというものね」と猫は饒舌に語り始めた。「……ってあなた、私の話、ちゃんと聞いてる?」
彼は開いた口をそのまま維持することしかできなかった。その猫の口元はもぞもぞと動いており、タイミングは彼の耳に届く言葉と一致していた。声の方向も、その口から発せられていると理解するしかなさそうだ。
「もしもし? 聞こえてる? うーん、……私の言葉はわからないのかな。所詮は猫の声帯だし」と猫は少し残念そうに首を捻った。
「あ、いえ、聞こえてますけど」
猫にこれ以上しゃべらせても、自分の頭は余計に混乱するだけだろう。彼はそう判断し、ひとまず応答することにした。
「日本語として明瞭に聞き取れてます。大丈夫です」
未知なる生き物に対して、彼の言葉は自然と丁寧なものになっていた。こういったときに強気に出られないことは彼のコンプレックスでもあったが、今はそんなことを気にしている場合でもない。
「なんだ、聞こえてるのね。よかった、それなら話が早いわ」と猫は言い、彼の左足に近付いて、よっこらしょ、といった感じで身体を横たえた。お世辞にもスマートな体型とは言えない。その姿は彼に、地元の神社でお正月の神事に奉納される、巨大な鏡餅を連想させた。
「突然ごめんなさい。えっと、どこから話せばいいのかな?」猫はうーんと軽く唸ってから続けた。「話すと長くなるから一言でいうと、……未来から来ました。よろしく!」
「いやあの急に『よろしく!』とか言われても困るんですけど」と彼は答えた。「……あ、でもとりあえずよろしくお願いします」
それから猫は、彼の目をじっとのぞき込んで尋ねた。
「あなた、名前は?」
「アツマです」
特に隠すこともないだろうと思い、彼は正直に自分の名前を答えた。
「石、持ってるわよね?」
「石?」……この猫は何を言っているのだろう?
「何色?」
「いや、なんのことだか……あっ」
「持ってるでしょう?」猫は確信があるかのように言った。「だって、私の声が聞こえるんだもの」
彼には心当たりがあった。何日か前、道端に落ちている小さな丸い石を拾った。表面に光沢のある鮮やかな青い色で、大きさはウズラの卵ぐらいだったと思う。確かジーパンのポケットに入れてそのまま……ということは、今も持っているかもしれない。
彼は左臀部にわずかな違和感を感じた。ポケットに左手を突っ込んでそれを探り当て、取り出して手にひらに置いた。あらためて眺めてみると、その石は幻想的な輝きを放っている。油断をすると、石に魅入られて魂を抜かれてしまうかもしれない。そんな気がした。猫が「私にも見せて」と立ちあがって首を伸ばしたので、彼は猫の目にも見えるように、腕を少し下げて手のひらを彼女の方に向けた。
「青。ブルー。……じゃああなた、アツマブルーね」と猫はさらっと言った。どうやらそれは、彼=アツマブルーということらしい。当然ながら彼は聞き返した。
「え? そ、それってどういうことですか?」
「あら、気に入らない? だったらブルーアツマでもいいわよ」と猫は勝手に話を進めていく。
「なんだったら、略してブルマーとかにする? あ、いいかもね! ブルマー。似合ってる」
猫は嬉しそうにまくし立てた。
「いやあの、ちょっとブルマーだけは洒落にならないっていうか。普通にやめてください。ちゃんと略せてないし」
彼は少し憮然として答えた。
「あら、気に入らない?」と猫は悪戯っぽく口元を綻ばせた。そして「じゃあ、アツマブルーで決まりね」と彼に告げた。