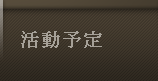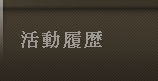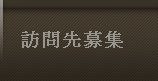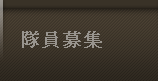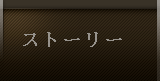ストーリー
第6話:金?
第1話← 第2話← 第3話← 第4話← 第5話← →第7話 →第8話 →第9話 →第10話 →第11話 →第12話 →第13話 →第14話 →第15話 →第16話 →第17話 →第18話
どれくらいの時間が過ぎたのだろう。しばらく呆然自失でその場に立ち尽くしていたアツマは、脇を通り過ぎる老婦人の視線を感じて我に返った。目を合わせると気まずい雰囲気が漂いそうだったので、「あれ、定期はどこかなぁ」などと呟きながら脇に置いたバッグをかき回した。怪しさをうまく誤魔化せたとは思えないが。
――とにかく、まずは大学に向かおう。もしもユッキーに会えれば、誤解を解くチャンスがあるかもしれない。それができなくても、夜に予定されている合唱団の練習までにはまだ時間があるから、混乱した頭を整理することぐらいはできるはずだ。
それにしても、ユッキーのあの反応から想像すると、彼女にはニボシの声が聞こえていなかったのかもしれない。そういえば、ニボシは最初にアツマに対して声を掛けたとき、自分の声が聞こえているかどうかを確かめていた。普通の人間には、ニボシの声は聞こえないということなのだろうか。
しかしそうすると、ユッキーが見ていたのは、猫に向かってひとりで話し掛け、猫の前で変身(呪文付き)をしようとして、さらにはその猫と抱き合っているアツマの姿だったということになる。思い返してみると(思い返したくもないが)、そこには絶望という名の深い暗闇しか見えない。もうだめだ。消えてなくなりたい。あるいはいっそのこと、本当に変身してしまいたい。ああ、自分ではない何者かになって、すべてをやり直すことができたらいいのに。
坂を上りきって駅前に出る。平日の午後3時の南大沢は、土日の騒然とした雰囲気と比べると、信じられないぐらいにのんびりとしている。それでも、改札の前には常に人の流れがあって、今も新宿方面からの電車が到着したところなのか、改札口から続々と人が出てきている。駅前のドーナツ店の前では、つがいの鳩が仲良く何かを啄み、それを3歳ぐらいの男の子が興味津々といった感じで眺めていた。近くで立ち話をしている女性のどちらかが彼の母親なのだろう。話に夢中になりながらも、男の子を視界にしっかりと捉えて見守っている。アツマの胸中とは対照的に、この世界はどこまでも明るく、どこまでも平和である。
視線を再び駅前に向けると、見慣れた顔が「おー、アツマじゃん!?」と右手を挙げながら近付いてくるところだった。アツマはその顔を見ただけで、心が少しだけ軽くなったような気がした。
「あ、タムタム。……あれ? 研究室は?」
「ん、今、休憩中。上島にでも行こうかと思ってさ」
彼の言う「上島」とは、駅ビルに入っている「上島珈琲店」のことだ。彼の休憩時間が何時間あるのかは知らないが、きっとそこでDSでもやるのだろう。
アツマとタムタムは大学の合唱団の同期で、二人ともこの春から大学院に進学した。専攻は、アツマが文系なのに対して、タムタムは理系。性格は、アツマが「まじめ」と言われることが多いのに対して、タムタムは「チャラい」が代名詞。正反対なキャラの二人だが、お互いに不思議と馬が合い、今でもちょくちょく顔を合わせている。アツマが新しく立ち上げた一般の合唱団にも、真っ先にタムタムがメンバーとして加わっていた。
「それよかさ、アツマ、お前、なんかあったの?」
タムタムが珍しく神妙な顔つきで聞いてきた。
「えっ、なんかって?」
「さっき、そこでユッキーとすれ違ったんだけど……」
アツマの前に再び暗闇が広がった。ユッキーだけならまだしも、彼女を介してアツマの所業が知れ渡っていくとすると、もはや手の打ちようがないだろう。果たして、ユッキーはどこまでタムタムに状況を伝えたのか。それを確認しなければならない。
「ユッキー、何か言ってた?」
まるで告白の返事を聞くようなドキドキした心持ちで、アツマはタムタムの次の言葉を待った。
「んー、お前のこと心配してたよ。で、なんとなく話は聞いたけどさ、えっとなんだっけかな、『メタモン』とか『へんしん』とか言ってたかな? お前、ポケモン始めたの?」
どうやらタムタムは豪快に誤解をしてくれているようだ。もしかすると、ユッキーは気が動転していて、状況をうまく説明できなかったのかもしれない。
このままポケモンの話を始めて誤魔化すこともできただろう。しかし、アツマはその瞬間、すべてを正直に話して、タムタムに相談に乗ってもらうのがベストだと判断した。信じてもらえるかはわからないけれど、この状況は、アツマがひとりで抱えるにはあまりにも重過ぎた。そして相談するなら、タムタムしかいない。
「いやいやいや、そういうんじゃなくてさ、実は……」
アツマは先ほどまでの出来事を掻い摘んで話した。喋る猫のこと、自分が拾った青い石とバスターガイザーのこと、それをユッキーに見られて誤解されていること……。もちろん、変身に関する具体的な件やニボシと抱き合った件は割愛した。
話を聞いていたタムタムは、途中から腹を抱えて笑い始め、手を叩きながらアツマにコメントした。
「いやー、アツマ、冗談きついって。どんだけ中二なの?」
「いや、それがさ、信じられないかもしれないけど、本当なんだよね」
「マジ? それ本気で言ってんの? だとしたらヤバいって。病院に行った方がいいんじゃない?」
言われてみると、さっきの出来事はすべてが幻だったような気もする。どちらが自分にとって幸せかはわからないけれど、少なくともこの世界にとっては、その方が平和だろう。ああそうか、自分は病気なのか。確かに、ここのところ相当、疲れが溜まっているような感じがする。
「そんなことよりさ、アツマ、これ見ろよ」
重大な問題をあっさりと脇に置いて、タムタムは話題を変えた。さすがである。彼はジャケットのポケットをしばらくまさぐると、そこから何かを取り出した。重量感があって眩しく輝くその球状の物体は、金色の何か……というよりは金そのものに見えた。
「見ろよこれ、俺が作ったんだぜ」と、タムタムは得意そうに言った。
「何これ? まさか金?」
「そう。俺、今、錬金術を研究しているんだけど、昨日はポケモンゴールドとハンバーグを実験機で混ぜてみたんだよね。で、今朝、研究室に行ってみたら床に落ちてた、ってわけ」
タムタムは興奮気味にまくし立てた。アツマは素直に感じた疑問を口にした。
「……なんでそのふたつを混ぜたの?」
「ん? ポケモンゴールドならゴールドってぐらいだから金になりそうじゃん。ハンバーグは触媒ってやつだな」
まったくもって意味不明だったが、もしかすると世紀の大発見はこういったチャラさが生み出すのかもしれない、とアツマは妙に納得した。タムタムは、アツマの疑問をサラッと流して話を続けた。
「まあとにかくよく見てみろよ。これだけでかい金の玉だぜ。すごいだろう? グレート金玉って名付けようかと思ってるんだ」
「(ここでは下ネタはやめて欲しいんだけど……。まあ、たまにはいいか(玉だけに)。)……でもさ、『落ちてた』ってことは、それって本当に実験でできたの?」と、アツマは第2の疑問をタムタムに投げかけた。
「きっと激しい化学反応で実験機から飛び出たんじゃない? いいじゃん、細かいことは」
あまり細かいことでもないような気がしたが、アツマはもはやそこは問わないことにした。
眩しさにも慣れたので改めてその玉を眺めてみる。その光は、よく見るとただ眩しいだけではなく、幻想的な淡い光に包まれている。直径は3cmぐらいだろうか。表面には光沢があって、質感としては、金というよりはむしろ宝石に近いかもしれない。
「あれ? でもこの形と光り方、どこかで見たような……」
そのとき、ふたりの足元から突如として声が聞こえた。
「それはまさしく、金のアートストーンね!」