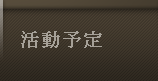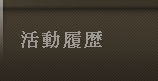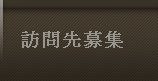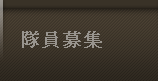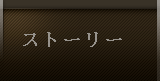ストーリー
第8話:告白
第1話← 第2話← 第3話← 第4話← 第5話← 第6話← 第7話← →第9話 →第10話 →第11話 →第12話 →第13話 →第14話 →第15話 →第16話 →第17話 →第18話
ふたりと一匹は夕暮れの南大沢を闊歩していた。西に傾きかけた太陽が、ニボシの純白の体毛を薄く朱色に染めようとしている。アツマとタムタムが並んで歩き、その数歩先をニボシがテクテクと進んだ。
結局、興奮したタムタムの質問攻めと、それにノリノリのニボシの掛け合いに圧倒され、ユッキーを探すどころか大学に行くことすら儘ならなかった。練習開始時間ギリギリのところで、ようやく移動に漕ぎ着けたところだ。歩きながらも間断なく会話は続く。
「つまり師匠は、そのギガスパイアってやつと26世紀で戦ってたわけっすよね? で、亜空間転送装置ってやつでこの世界に来たという」
「そう。アートストーンと一緒に」
「でもなんでこの時代のこの場所だったんすか? 西麻布とか、もっとコジャレたとこにすればよかったのに」
タムタムがなぜ西麻布を例に挙げたのか聞いてみたい衝動に駆られたものの、アツマはここで話の腰を折るのは得策でないと考えスルーした。
「場所に関しては、転送元と同じ地点。つまりここに研究所があった。……過去形にするのも変だけどね、そういうこと。時代については、設定したのは私じゃないから、正直、よくわからない」
ここに研究所、ということは、この場所で26世紀には戦争が行われるということなのだろうか。ニボシは具体的なことをまだ教えてくれていないけれど、戦争ということは、人も、街も、きっと何もかもが無事では済まなかっただろう。想像するのは難しい。しかし、それは堪らなく悲しい情景だ。たとえ、それが自分のいなくなった後の遥か未来の出来事であったとしても。
翻って、ニボシの目にはこの「過去」の平和な南大沢はどのように映っているのだろうか。尋ねてみたい衝動に駆られる。でも、それはきっと勇み足だ。
「まあとにかく、俺たちがギガスパイアの誕生を阻止して、未来を平和にすればいいわけっすよね?」
タムタムは相変わらずの調子で会話を続けている。
「うん。……そういうこと」
「しゃー、マジ熱いわ、それ。やったろうじゃん。なあ、アツマ?」
「……あぁ、そうだね」
アツマはこの点に関しては腑に落ちていない部分がある。もちろん、もしも自分の手で未来の戦争を回避できるのだとしたら、喜んで協力したいとは思う。でも、果たしてそんなことは可能なのか。学部時代に一般教養の哲学の授業で学んだような気がしないでもないタイムマシンのパラドクスが頭を過る。
仮にギガスパイアの誕生を阻止したとすると、ニボシがいた「未来」はどうなってしまうのか。新しい「未来」に書き換えられるなんてことは起こり得るのか。……いや、そうなると、今、目の前にいるニボシがこの世界にやってくることはなくなって、そうするとギガスパイアはやっぱり生まれることになって……。
これがだめだとすると、いわゆるドラゴンボール的な未来分岐説が妥当なのだろうか。……いや、確かこの説にも、かなり致命的な矛盾があったはずだ。例えば、もしも未来が分岐可能ならば、分岐は無限に起こり得ることになる。そこをタイムマシンで移動しようとすれば、無数の「未来」から無数の人間がやってくる一方、こちらからはどの「未来」に行くのかが選択できない。
確か授業のときには、このあたりで思考を放棄して「よってタイムマシンは存在し得ない」と結論を出した記憶がある。しかし、目の前にこうやって現実を突きつけられると、否応なく再び頭を巡らせなければならない。この問題が解決しなければ、おいそれと「ギガスパイアの誕生を阻止」などとは言えない。アツマはそういう性格だ。
ニボシはどうなのだろう。彼女はその答えを知っているのだろうか。アツマはタイミングを見計らって二人の会話の間に入った。
「それで……ギガスパイアの誕生を阻止したら……未来は変わるのかな?」
「なに言ってんの? そりゃ変わるに決まってんじゃん」
即答したのはタムタムだった。ニボシは立ち止まり、振り返ってアツマの顔を見上げた。そして彼と目を合わせて、少し困ったような表情を作ってふっと微笑んだ。
「……どうなんだろうね」
「……わからないの?」
アツマとタムタムも足を止めてニボシを見返した。
「それはこっちに来てからずいぶん考えた。でもね、結局はわからなかった」
「……だったらなんで、ギガスパイアの誕生を阻止しようとするの?」
「……もう来ちゃったから。ここに。……もう後戻りはできないの。どうなるかわからないけど、とにかくギガスパイアの誕生を許すわけにはいかない」
ニボシの瞳には、決意の炎が淡く静かに燃えていた。
「元の世界に戻りたいとは、思わない? もしも過去を変えたりなんかしたら、自分の来た世界がなくなっちゃうかもしれないんだよ?」
アツマのその問いかけに、ニボシは視線を外して横を向いた。そして小さな声で呟いた。
「……もう、戻れないから」
夕日がニボシを背後から照らす。ちょうど影になって彼女の表情を読みとることができない。
「戻れないの? 転送装置がこっちにはないから?」
「……違う。転送装置の問題じゃない」
「それとも、猫になっちゃったから?」
「……おしいけど、それもちょっと違うかな。……っていうか、説明するの難しいなあ。アツマはホントに難しい質問ばかりするんだから」
ニボシは答えをはぐらかすような感じで笑った。
「じゃあ師匠、俺から質問してもいいっすか?」と、タムタムが割って入る。
「うん。どうぞ」
「師匠って、おいくつなんですか?」
タムタムの脈略のない質問に、アツマは自分の知りたいことがまた遠ざかっていくことを覚悟した。
「……レディに対してよくもそんなことを聞けたものね」と、ニボシはあきれた顔をして笑った。
「いや多分、アツマが知りたがってんじゃないかな、と思いまして」
確かに、それはアツマも気になっていたことだった。話している時の感じから、同年代か、やや年上ぐらいだろうと勝手に推測してはいたものの、言われてみれば、彼女の年齢を確認していない。それどころか、彼女のプライベートに関する一切の質問は、これまでことごとくかわされ続けてきていることに気付いた。
「アツマ、知りたいの?」
「……いや、べつに知りたくなんか」
「53」
「……」
「……」
「……えっ??」
アツマの声は思わず裏返った。
「同い年ぐらいだと思った? ……残念! 猫になったのを機に若づくってみたのでした! どう? 引いた?」
ニボシは挑発的な視線をアツマに投げかける。
「……べつに引かないよ。年なんか関係なく、ニボシは、……ニボシでしょ?」
何かぎゅっと、胸が締め付けられたのは確かだ。
「強がってない?」
「強がって……ないと言えば嘘になるかも」
「うん。ふふ、正直でよろしい」
「ありがとう」
言葉のキャッチボールが素直に楽しい。まるでずっと昔からの友だちと話しているようだ。
「さて、さあ! 二人とも! もうそこが練習会場なんでしょ!? 早く行きましょう!」
ニボシはそう言って、フレスコの入口に向かう階段をぴょんと登って行った。